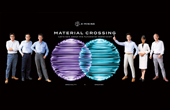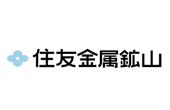太陽光の可視光線を透過させながら、熱をもたらす近赤外線のみを吸収・カットする特性を持つ画期的な素材を開発した住友金属鉱山。すでに事業展開が四半世紀になろうとするこの素材を今、同社はアパレル分野など新規領域に展開しようとブランディング戦略に力を入れている。
千葉市の幕張メッセで10月初旬に開かれた「農業WEEK」。その一角にブースを設けた住友金属鉱山は、2023年秋から本格展開してきた「SOLAMENT®(ソラメント)」というブランドで、新素材の売り込みを図っていた。
地上に降り注ぐ太陽光のうち、約42%を占めるのが近赤外線だという。皮膚やモノに太陽光線が当たって温かくなるのも、この近赤外線があるからだ。寒い冬にはありがたいが、過酷な猛暑に毎夏襲われる日本では近赤外線のコントロールが「暑さ対策」の大きなカギを握るといえる。
SOLAMENTは同社が約20年前に開発した近赤外線の制御技術を、素材ブランドとして確立しようとする試みである。この素材SOLAMENTは自動車や建築用フィルムに使われ、すでに世界市場で実績を上げている。だが、住友金属鉱山はあえて従来のBtoB型ビジネスモデルから脱却し、消費者に直接訴求するブランド戦略へと舵を切ったのだ。
背景には、素材業界を取り巻く環境の激変がある。膨大な時間と資金を投じて10〜20年をかけて開発してきた素材でも、競合他社による模倣が早く、製品はあっという間に陳腐化する。しかも収益回収期間の短縮を求める株主からの要求が高まるなど投資環境も大きく変化し、長期投資はますます困難になっている。
技術による差異化だけで生き残るのは、もはや難しい。そこで住友金属鉱山は、オンリーワンで真似されにくい技術力のある素材をブランディングによって価値を高めようと考えた。「SOLAMENTにおいては技術開発よりもブランディングの方が短期間でレバレッジが効く」――そう判断したのだ。
SOLAMENTのブランド戦略で特徴的なのは、アパレル分野を最初の突破口に選んだことである。素材メーカーである住友金属鉱山にとって、ブランド戦略導入前はアパレル分野での想定顧客は繊維メーカーのみだった。だが素材が活用されて「良いもの」であるという価値を決めるのは、服飾製品などをつくる最終製品メーカーや消費者だ。そこで、まず消費者における素材価値を高めることで、実際の取引の後押しとする「BtoCtoB」を目指し、戦略的にブランドを確立するには消費者に直接届くアパレル領域が最も効果的だと考えた。
BtoB企業であり、これまで消費者との接点がなかった住友金属鉱山。近赤外線吸収素材のスペックをアピールしても、アパレル業界からの問い合わせは年間わずか2件だったという。しかし、2023年のリブランド以来、「服飾などの自社製品に新たな付加価値を乗せられるのではないか」と問い合わせしてくる件数は数百件にも達する。2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)の住友館パビリオンに併設されたショップで販売されたSOLAMENTを活用して遮熱効果を高めた晴雨兼用傘は、1本1万2100円(税込)という高価格ながら、あっという間に400本が完売したという。
こうした効果もあり、スノーピークなどのアウトドアブランドとの協業も進み始めた。
また、この素材をファン付き作業着の布地に使ったところ、一般的な作業着と比べた際最大で19.3度も着内温度が下がった例もあった。
すでに農業分野では石川県に拠点を置く能任七(のとしち)が「青天張」という遮熱ネットを開発した。これを張ったビニールハウスの地温は夏場、最大で8.5度下げることができる。熱のもととなる近赤外線をカットするため、猛暑の夏場に「普通なら暑くて避けるハウスの中に逆に避難する」という農家も出てきたという。
ただし、住友金属鉱山が狙うのは大量生産・大量消費の市場ではない。同社がベンチマークとするのは、アパレル分野で素材ブランドとして確立した「GORE-TEX®(ゴアテックス)」だ。ハイブランド市場を狙い、高級市場から技術を浸透させていく――これがブランディングを担うSOLAMENTの戦略だ。
住友金属鉱山は消費者に近いアパレル市場に接近するため、この分野では160年の歴史を持つ繊維商社、瀧定名古屋(名古屋市)と組んだ。素材開発から糸の構造、織り方に至るまでを教わりながら一緒に開発していくという、実質的な共同開発が可能になるからだ。
SOLAMENTという素材は無機材料であるため耐候性が高い。耐久性という物理的な強さを武器にすれば、消費財と組みわせることで無形の価値を積み上げていくことができるかもしれない。
住友金属鉱山が目指すのは、単なる素材の拡販ではない。これはSOLAMENTを通じて素材メーカーの新しい生き方を模索する、壮大な実験なのである。


 JP
JP






 ジャーナリスト三河主門が住友のDNAを探る
ジャーナリスト三河主門が住友のDNAを探る